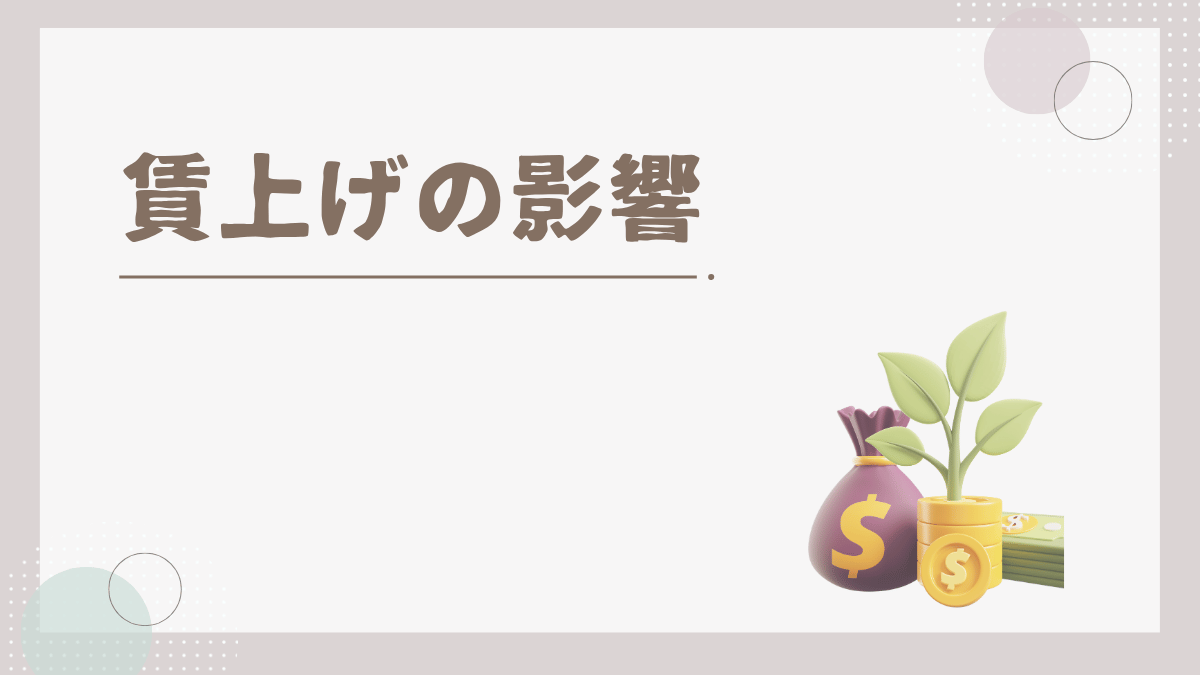ニュースで「最低賃金が上がった!」という話題があると「お給料が増えるのは嬉しいけど会社は大丈夫なのかな?」「人件費が上がるってことは人員整理とかパートや派遣切りが増えちゃうのかな…?」
そんな不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。とくに30代、40代にとっては自身の働き方や家計に直結する話ですから気になりますよね。
前職では人事戦略部門で働いていたので、いろんな会社の内情や業界の動きについて情報交換できる人脈があるんです。普通は表に出てこない人事政策の裏側や各社の本音についてみなさんにシェアしたいと思います。
日本の「深刻な人手不足」があるため企業は「大規模な人員整理」をしたくてもできない状況。この記事ではその理由を詳しくお伝えしていきます。
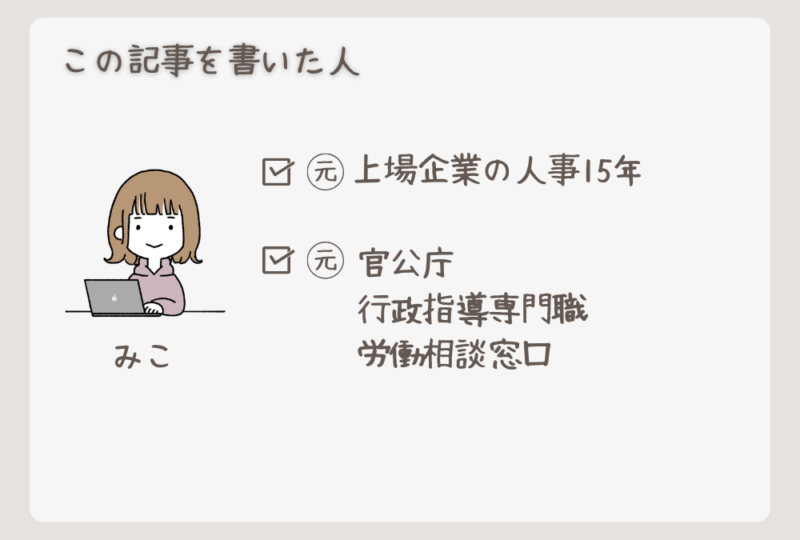
会社が直面する「二重のプレッシャー」

まず会社が最低賃金アップでどんな状況に置かれているか想像してみてください。当然、従業員のお給料が上がれば会社にとっては「人件費」というコストが増えますよね。
さらに最低賃金より少し上のお給料をもらっていた人たちも「自分たちも上げてほしい」となりますから全体の賃金水準が上がる「連鎖反応」も出てくるんです。
会社としてはこのコスト増は頭の痛い問題。利益率が薄い中小企業にとってはかなり大きなプレッシャーに。 でも、ここで一つ日本ならではの「大きな壁」があるんです。それは「深刻な人手不足」
今はどの業界も「人が足りない!」と悲鳴を上げている状況ですよね。コンビニも飲食店も介護の現場も、どこもかしこも人手不足。
つまり会社は「人件費を抑えたい」という気持ちと「人がいないと仕事が回らない」という現実のまさに「二重のプレッシャー」に挟まれている。
この「人手不足」という現実が皆さんが心配している「安易な人員整理」を実はかなり難しくしているんです。だって、せっかく辞めてもらっても新しい人を雇うのが本当に大変。元人事としてはその苦労は痛いほど分かります。
会社が取る具体的な「3つの戦略」
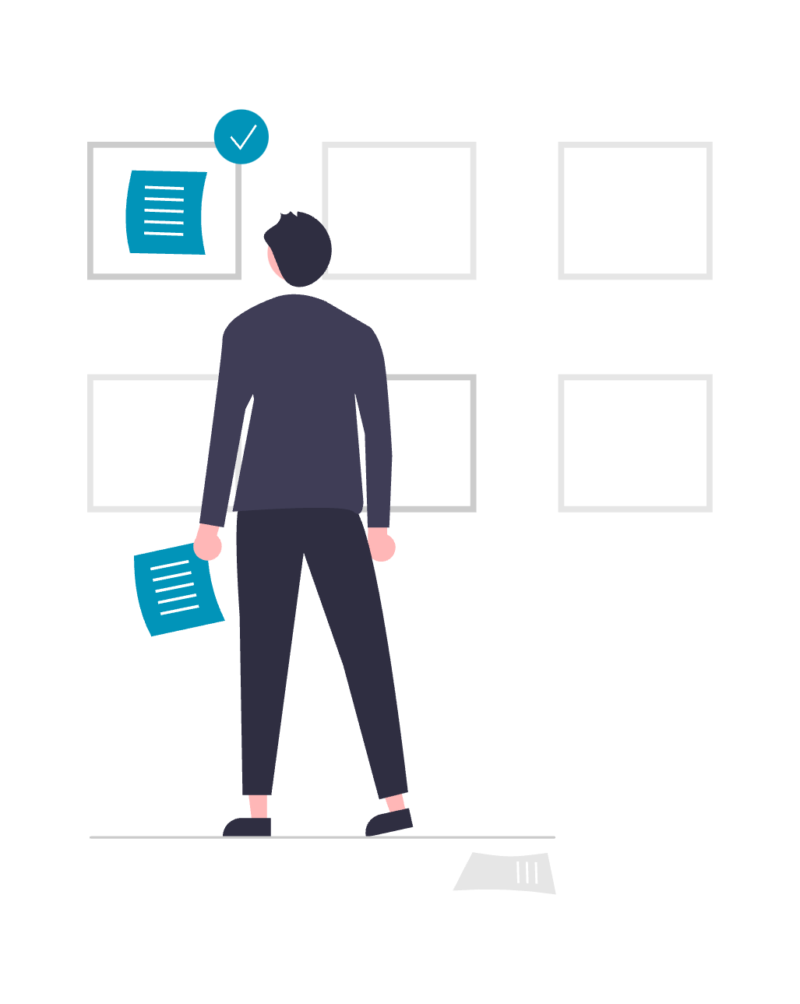
では会社はこの二重のプレッシャーの中で具体的にどんな手を打ってくるのでしょうか。
大きく分けて3つの戦略が考えられます。
戦略1:人を「切る」より「活かす」方向へ
みなさんが心配している「人員整理」ですが先ほどお話しした「人手不足」のせいで大規模な解雇は考えにくい。
むしろ会社は今いる人をどうにかして「活かす」方向に動きます。
予測される企業戦略を整理しました。
| 戦略カテゴリ | 特定の戦略/行動 | 目標 | 雇用への影響 |
| 労働コスト管理と人員調整 | パートタイム労働時間の短縮 | 直接的な賃金総額の削減 | パートタイム労働時間の減少 |
| パートタイムから正社員への転換 | 人材の確保、定着率向上 | 正社員雇用の安定化、パートタイム比率の低下 | |
| 労働生産性の向上(研修・スキル開発) | 労働力効率の向上 | 従業員のスキルアップ | |
| 業務効率化と技術導入 | 自動化とデジタル化の加速 | 人件費削減、労働力依存度低下 | 定型業務の減少、技術操作・保守職の需要増 |
| プロセス再構築とムダの削減 | 業務効率の最大化 | 効率化による人員再配置または削減 | |
| 価格戦略と収益創出 | 製品/サービス価格の調整 | 増加コストの回収 | 雇用への影響は限定的 |
| 高付加価値製品/サービスへの注力 | 利益率の向上、差別化 | 高付加価値業務への人員シフト | |
| 戦略的ビジネスモデル転換 | 業務の移転またはアウトソーシング | 労働コストの最適化、柔軟性の確保 | 国内雇用の一部減少、外部労働力への依存増 |
| 事業ラインの見直し/市場セグメントの再評価 | 収益性の最適化、競争力強化 | 低利益率部門の人員削減、高利益率部門への集中 | |
| 合併・買収(M&A)による規模の経済追求 | 規模の経済、競争力強化 | 統合による人員再編の可能性 |
戦略2:テクノロジーで「効率化」を加速
スーパーや飲食店で「セルフレジ」や「配膳ロボット」を見かけることが増えましたよね。あれも、まさにこの最低賃金アップと人手不足が背景に。
会社は人件費の上昇を吸収するために積極的に機械やシステムに投資します。レジ打ちや品出し、清掃、簡単な問い合わせ対応などこれまで人が手作業でやっていたことをロボットやAIに任せるという動きが加速。
ただ機械を入れるだけでなく仕事のやり方そのものを見直す会社も増えます。例えば書類の電子化を進めたりオンライン会議を増やしたり。無駄な作業をなくしてより少ない人数で効率的に仕事を進めるための工夫。
これは単に「人件費を削減したい」というだけでなく「そもそも人が集まらないから機械に頼るしかない」という会社側の切実な事情。
私たちの仕事もこの変化に合わせてより「人間にしかできないこと」にフォーカスしていく必要が出てくるかもしれません。
戦略3:価格に「転嫁」でもそれだけじゃない
会社が人件費のコスト増を吸収する一番手っ取り早い方法は製品やサービスの「値上げ」みなさんも、いろんなモノが値上がりしていると感じてますよね。
小売業や飲食業など人件費の割合が高い業界では値上げは避けられない動き。でもただ値上げするだけだとお客さんが離れていってしまいます。
そこで会社は「この値段でも買いたい!」と思ってもらえるように製品やサービスの「価値」を高めることに力を入れます。
例えば、より高品質な素材を使ったり特別なサービスを付けたり新しいメニューを開発したり。 私たち消費者もただ安いものを選ぶだけでなく「この値段を出す価値があるか」をより吟味する時代になっていくということかもしれません。
業界ごとの「明暗」と「私たちの働き方」
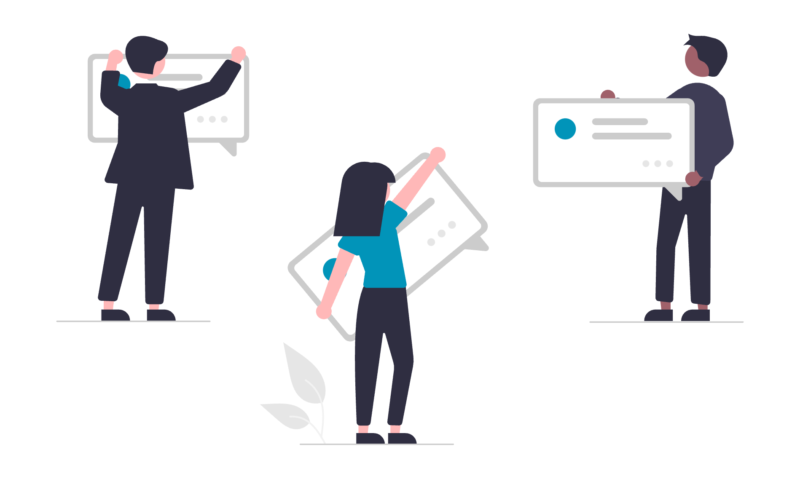
この最低賃金アップの影響はすべての業界で同じように出るわけではありません。影響が大きい業界 パートやアルバイトの割合が高く利益率が薄い「小売業」「飲食業」「宿泊業」「介護サービス業」などは特に大きな影響を受けます。
これらの業界では自動化がさらに進みサービスの提供方法も大きく変わっていくでしょう。例えば、介護の現場では見守りシステムや移乗支援ロボットの導入が進むかもしれません。
| 業種 | 主な特徴 | 最低賃金引き上げの影響 | 予測される対応 |
| 小売業、飲食業、宿泊業 | 高いパートタイム比率、薄い利益率、労働集約型 | 高い直接コスト圧力、賃金波及効果 | 自動化(セルフレジ、ロボット)、労働時間短縮、価格引き上げ、パートタイムから正社員への転換 |
| 介護サービス業 | 労働集約型、人手不足深刻、公定価格の影響 | 高い直接コスト圧力、人材確保の困難さ | 自動化(見守りシステム、移乗支援)、生産性向上、人材定着策、賃上げによる人材確保 |
| 製造業(高度自動化) | 高い生産性、熟練労働者中心、自動化進展済み | 直接的な影響は限定的、間接的なサプライチェーン圧力 | 自動化の最適化、熟練人材の賃金維持、サプライチェーン最適化 |
| IT/専門サービス業 | 高い平均賃金、知識集約型、高利益率 | 直接的な影響は限定的、賃金波及効果(中堅層) | 優秀な人材の定着、スキル開発への投資、グローバル競争力強化 |
一方で平均賃金が高くもともと自動化が進んでいる「製造業(高度な技術を使う分野)」や「IT業界」「専門サービス業」などは直接的な影響は限定的。
これらの業界では、むしろ優秀な人材を確保するための賃上げ競争が続くかもしれません。 みなさんの仕事がどの業界にあるかによって受ける影響も変わってきます。
自分の仕事が今後どう変わっていくのか考えてみるいい機会かもしれませんね。
政府の「後押し」と「社会の変化」
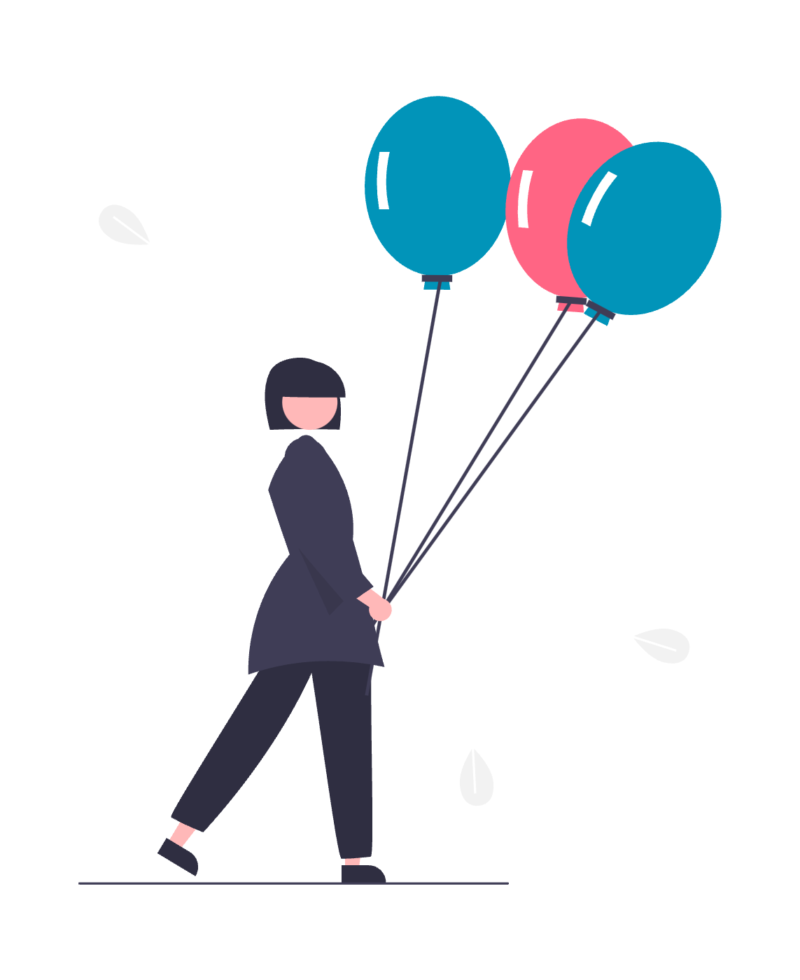
政府も企業がこの変化に対応できるよう様々な支援策を打ち出しています。たとえば生産性向上を支援するための補助金制度などですね。(参考:厚生労働省 令和7年度業務改善助成金のご案内)
会社側も単にコストを削減するだけでなく「企業の社会的責任(CSR)」という視点を持つようになっています。安易な人員整理は会社のイメージを大きく損ないますし従業員の士気も下がってしまいますから。
だからこそ短期的なコスト増があっても従業員を大切にし長期的な視点で投資を続ける会社が増えていくはず。 もちろん最低賃金が上がっても物価も同じように上がってしまっては生活は楽になりませんよね。
政府はこの「賃金・物価スパイラル」が起きないよう実質的な購買力が上がるように経済全体を注意深く見守っていくことになります。
さいごに:最低賃金アップは「変化のきっかけ」

最低賃金アップは確かに企業にとって大きな変化の波。不安を感じる方もいるかもしれませんが日本が抱える「深刻な人手不足」という現実がみなさんが心配するような「大規模な人員整理」の大きな歯止めになっているということをお伝えしたかったんです!
むしろ会社は今いる人材を大切にしテクノロジーを駆使して「もっと効率よく、もっと価値のある仕事」を生み出そうと必死。
私たち働く側もこの変化の波をチャンスと捉え新しいスキルを身につけたり自分の仕事の価値を高めたりする意識がこれまで以上に大切になってきますね!
これからの働き方を考えるうえで少しでもお役に立てたら嬉しいです。