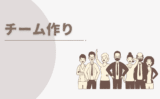「えっマジで?アイツが上司に!」なんてマンガみたいなことが現実にも起こりうるのが会社というもの。今まで部下だった人がある日突然、自分の上司になる。これって結構複雑な状況。
昇進の理由は未知の実績や新プロジェクトでの抜擢、単なる組織の都合などさまざま。でも理由はどうあれ「元部下が上司」という状況は色んな感情や課題を引き起こしがち。
「なんでアイツが…」ってモヤモヤしたり「今まで通りに接していいのかな?」って戸惑ったり。
この記事はまさにそんな複雑な状況に立たされた方に向けて書きました。元部下が上司になったときにどう受け止めて行動すればいいのか。具体的な方法やよくある困りごとへの対処法を解説していきます。
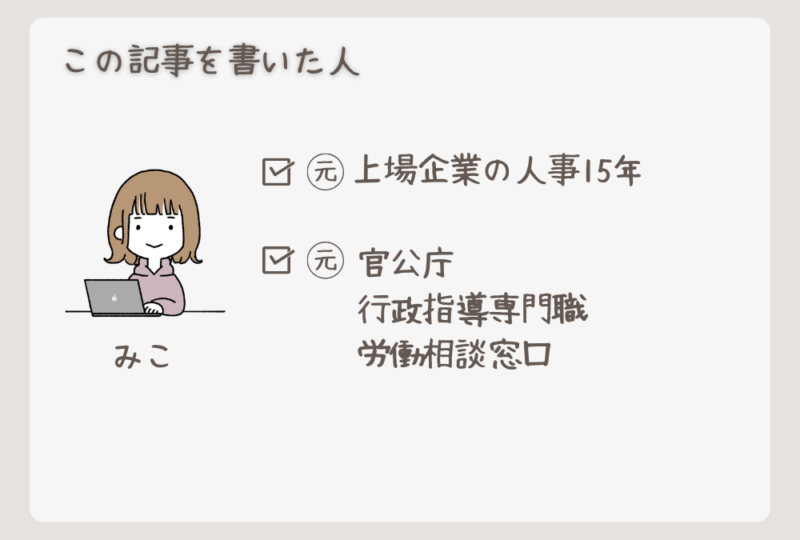
元部下が上司になったとき元上司はどう対応すべき?

元部下が上司になったとき、お互いが気持ちよく働けるようにするにはどうしたらいいのでしょうか?新しい関係をうまく築いていくためのヒントをご紹介したいと思います。
「理想論を並べられても…」と思いますよね。確かに現実は深い。でも辞めるわけにはいかない。実際の職場で活用できる具体的な対応方法をシチュエーション別にお伝えします。
元上司が心がけるべきポイント
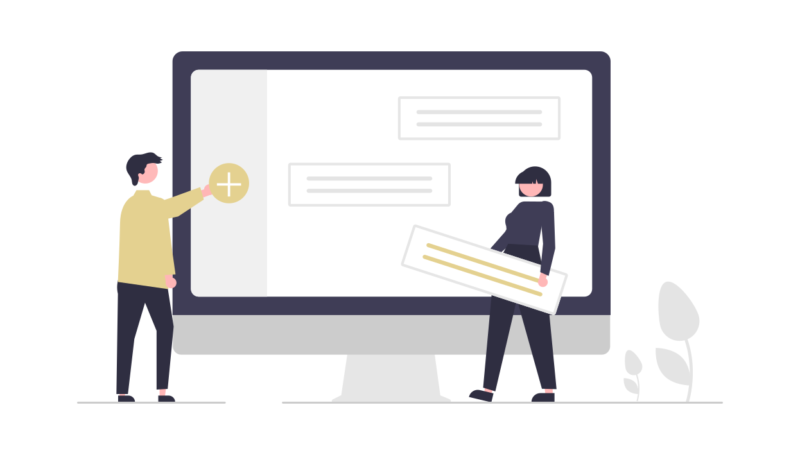
「え、アイツがうちのボスか…」正直、複雑な気持ちになるのも無理はありません。 今まで自分が教えてきた相手が自分の上に立つことになる違和感。もしかしたら悔しさや嫉妬、焦りを感じる人もいるかもしれません。
「自分のキャリアは、もうここまでなのか…」と不安になる気持ちも理解できます。 でもここで感情的になってしまうと自身の評価も下げてしまうことになりかねません。 ここはグッとこらえてオトナの対応を心がけましょう。
新しい役割を受け入れ協力的な姿勢を示そう
まずは新しい上司の役割を受け入れ協力的な姿勢を示すことが大切。「これからは〇〇さんの指示に従ってチームに貢献していきたいと思っています」 というように前向きな言葉で伝えることで新しい上司も安心するはず。
自分の気持ちを押し殺して相手に合わせるのは簡単なことではありません。もしかしたら「本当は自分が上に立つべきだったのに…」という思いを抱えているかもしれません。
ここは勇気を出して新しい上司のリーダーシップを受け入れ協力していく道を選ぶことが自身の成長にも繋がるはずです。
これまでの経験を活かし積極的に意見を発信しよう
長年培ってきた経験はチームにとって貴重な財産。新しい上司の指示を待つだけでなく「この件に関しては以前〇〇という方法でうまくいった例があります」というように積極的に意見やアイデアを伝えていきましょう。
ただし過去のやり方に固執するのではなく新しい上司の意見も尊重しながらより良い方法を見つけていくことが大切。あなたの経験は決して無駄ではありません。
過去の成功体験は新しい上司にとってもチームにとっても大きな助けになるはず。 経験だけに頼るのではなく常に新しい情報や知識を吸収し柔軟な発想を持つことも忘れないでください。
新しい上司のリーダーシップを尊重する
新しい上司には新しいやり方や考え方があります。 「前はこうだったのに…」と不満を言うのではなくまずは新しい上司のリーダーシップを尊重しそのやり方を見守ることが大切です。
もちろん明らかに問題がある場合は感情的にならずに具体的な事実を伝えて改善を促す必要はありますが基本的には新しい上司をサポートする姿勢でいましょう。

新しい上司は、これまでとは異なる知識や経験、視点を持っていて例えばDX推進やAIを活用した業務改善など今まで触れる機会のなかった新しい取り組みについて学べるかもしれません。
若い世代特有の柔軟な発想や最新のマネジメント手法から仕事の進め方について新しい気づきを得られる可能性も。
感情をコントロールしプロフェッショナルな対応を心がける
大切なのは感情的にならないこと。「なんでアイツが上司なんだ!」「昔は俺の方が仕事ができたのに!」みたいな気持ちはグッと飲み込んで常に冷静にプロフェッショナルな態度で接しましょう。
感情的な発言は周りの人たちを不快にさせるだけでなくあなた自身の評価を下げることにもつながります。悔しさ、嫉妬、焦り、不安…色々な感情が渦巻いているかもしれません。
感情に任せて行動すると後で必ず後悔することになります。状況が受け入れられないなら退職も選択肢の一つ。残る決意をしたのであればマイナス思考は捨てましょう。チームの足かせとなるような行動は避けるべきです。
サッカー日本代表・長友佑都選手の事例

サッカー日本代表の長友選手は長年にわたってチームを支え多くの若手選手の模範となってきました。新しい世代の台頭を素直に受け入れ自身の役割を柔軟に変化させながらチームに貢献し続ける姿勢はビジネスパーソンにとって優れたお手本。
長友選手は豊富な経験から的確な判断を下し幾度もチームのピンチを救ってきました。その知見はチームの貴重な財産。若手選手たちも彼から多くを学んでおり同様に自身の経験を活かして積極的に意見を発信。
ときには自分の考えと異なる場合でもチームの勝利のために全力を尽くす。この姿勢は新しい上司のリーダーシップを尊重し組織の目標達成のために協力することの大切さを示しています。

感情に左右されることなくチーム全体のために行動する姿勢はプロフェッショナルとして模範的。新しい世代を育てながら自身の役割を柔軟に変化させる彼の姿勢は組織の世代交代における良いモデルケースです。
スポーツ界と同様に企業でも異なる年齢層の組み合わせが相乗効果を生み出すことがあります。サッカー日本代表チームでベテランと若手が互いを高め合うように職場での世代を超えた絆づくりのコツを紹介した記事はこちらです。
よくある「困ったこと」解決策
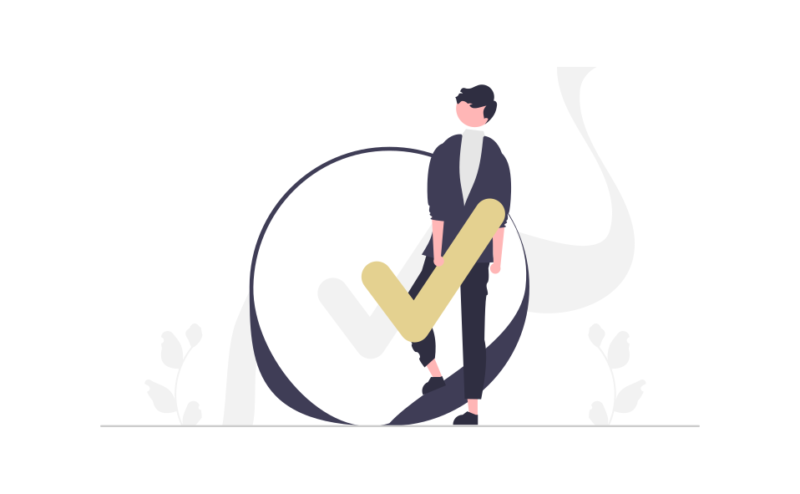
「元部下が上司」という状況はいろいろな問題が起こりがち。ここでは抱えるであろう「よくある困りごと」と「その解決策」を具体的に解説していきます。
元上司としてのプライドとの向き合い方
「正直言ってこの状況はムカつく。年下の元部下に指示されるなんて…」そんなイライラや悔しさを感じるのは自然なこと。長年積み上げてきたキャリアやスキルがまるで認められていないような気持ちになり胸が締め付けられることもあるでしょう。
でも、そのプライドが足かせになって仕事の質を落としたりチームの雰囲気を悪くしたりしては本末転倒。大切なのは今の自分の立場を冷静に受け止め「自分の経験やノウハウをどうやってチームの成長に活かせるか?」という建設的な視点を持つこと。それこそが本当のプライドではないでしょうか。
周囲の反応への対処法
「〇〇さんが新しい上司に就任したって聞いたよ」「今までとは雰囲気が変わるのかな」「部署の方針はどうなるんだろう」など職場では様々な噂話が飛び交うことが予想されます。このような状況下では、周囲の声に振り回されることなく、冷静さと専門性を保った対応を心がけましょう。
落ち着いた態度で日々の業務に取り組み変わらぬプロフェッショナリズムを示すことで、むしろあなたの存在感は一層際立つことでしょう。同僚たちからも「さすが経験豊富な先輩、この状況でも動じないんだな」と尊敬の眼差しを向けられるはずです。

何より重要なのは、一時的な噂話に惑わされることなくこれまで培ってきた経験と知識を活かしながらプロフェッショナルとして自分の職務に専念することです。そうすることで組織全体にとってもプラスの影響をもたらすことができます。
新しい上司とのコミュニケーションを円滑にするには?
「何を話したらいいか分からない…」新しい上司とのコミュニケーションに悩む人もいるかもしれません。じつは元部下である新しい上司も同じように悩んでいることが多いもの。以前のような気軽な関係は難しくなるかもしれませんがお互いが気を遣い合って不自然な関係を続ける必要はありません。
まずは共通の話題から自然に会話を始めましょう。時事的な話題や仕事に関連する軽い会話から入ることで、コミュニケーションが取りやすくなります。
また上司の得意分野について質問しアドバイスを求めることで、より自然な関係を築けます。相手を頼る姿勢を見せることでお互いの緊張も和らぐでしょう。
ときにはリラックスした雰囲気でお話ししてみるのはいかがでしょうか?例えばランチや仕事帰りの気軽な一杯を通じてお互いの思いを自然に分かち合える素敵な時間が生まれるかもしれません。
率直な気持ちの共有がお互いの距離を縮めてくれるでしょう。なにより豊富な経験を持つ先輩だからこそ余裕のある態度で関係をリードする姿勢はカッコいい。
信頼関係を築くには時間と努力が必要

信頼関係は、一朝一夕には築けません。日々の積み重ねの中で少しずつ育んでいくもの。 相手を尊重し誠実な態度で接することで時間はかかるかもしれませんが必ず信頼関係を築くことができるはずです。
最近読んだ本のなかでおすすめの一冊をご紹介させていただきます。ベストセラー「冒険する組織のつくりかた:軍事的世界観を抜け出す5つの思考法」人気なので知ってる方が多いですよね。
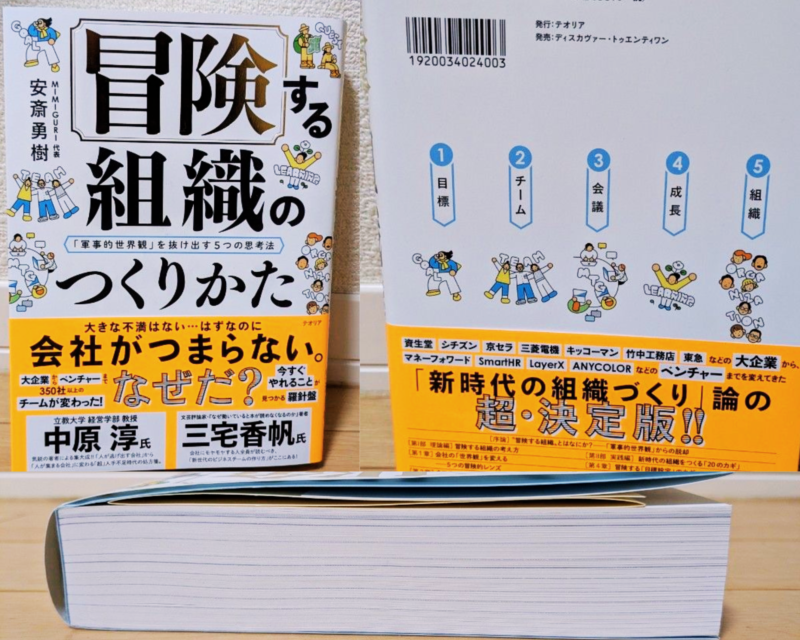
読みやすい文章と理論に基づいた具体的なアドバイスの豊富さ。とくに職場での人間関係や組織の悩みについてモヤモヤした気持ちに寄り添いながら優しく解決策を提示してくれます。ぜひ手に取ってみてください。
事例|元部下や同僚が上司になった人たち
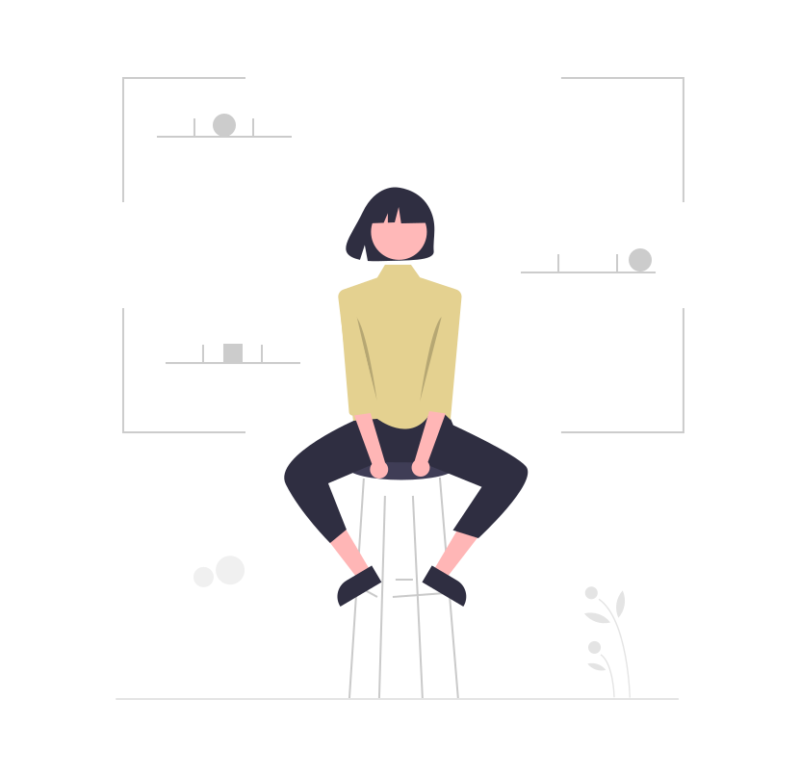
前の会社での経験から元部下が上司になった際の印象に残る事例を2つご紹介させていただきます。私自身が実際に目にしその後の展開まで見届けた貴重な経験。それぞれのケースでは「どのように状況に向き合い」「どんな解決策を見出したのか」具体的にお伝えします。
10年来の同期が突然上司になったケース
ある社員の専門プロジェクトを同期が新しい上司として担当することになったのです。専門分野で指示を受けるという難しい立場に置かれました。
周囲からは「働き続けられないだろう」「転職するしかない」といった否定的な声が多く上がりました。でもその社員は冷静に状況を受け入れ仕事に集中。新しい上司とも適切な距離感を保ちながら関係を築きました。その姿勢と実績が評価され3年後には別事業部の統括リーダーに抜擢。
新人だった部下が自分の上司に昇進したケース
あるベテラン社員は新入社員の育成担当をしていました。新人にビジネスの基本を教え定期的な面談で成長をサポート。3年後、驚くことに教えていた新入社員の一人が上司に。指導する立場から評価される立場への急な変化に周囲も心配。
でもベテラン社員は「上司をサポートする」という役割に切り替え新しい関係の中で自分の強みを活かす方法を見つけていきました。この姿勢のおかげで互いを認め合える関係を築き定年まで充実した仕事生活を送ることができました。
なぜ彼女らは転職を選ばなかったのか。それは「常に優秀でなければ」という思い込みを手放したから。これは予期せぬ困難に直面したときの大切な教訓となりました。
「常に優秀でなければ」という思い込みから自由になる

「会社では常に優秀でなければならない」という価値観に縛られている人もいますがそういった考えから自由になることが必要な時期って訪れます。
40歳を過ぎれば体力や気力の変化は自然なこと。調子が悪い日があるのも当然です。人生の折り返し地点では心と体の限界を受け入れ無理のない働き方を見つけることが大切なのです。
早期退職や起業|衝動的な決断の落とし穴
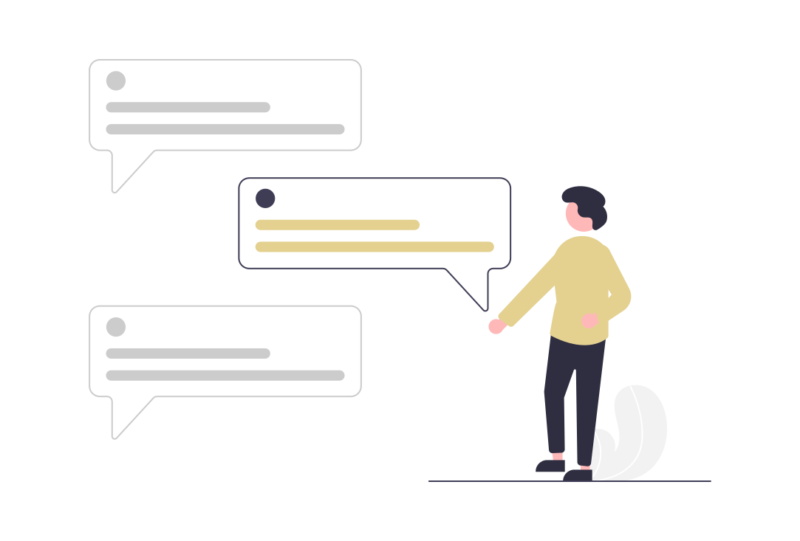
「元部下が上司」「年下が上司」という状況に戸惑い退職を考えている方もいるでしょう。その決断が本当に最善なのか立ち止まって考えてみてください。
「新しい生き方」を求めて早期退職や起業を選ぶ方もいますが十分な準備なく決断するケースも見られます。焦りから衝動的な決断をしがち。安易な決断は心身の疲労や経済的な困難を招きかねません。
モヤモヤを抱えているベテラン社員は「急ハンドル」を切るのではなくまずは自分の気持ちと向き合い十分な休養を取りながら将来をじっくりと考えることをおすすめします。
悩みがあるときは「悩む自分」を責めすぎない
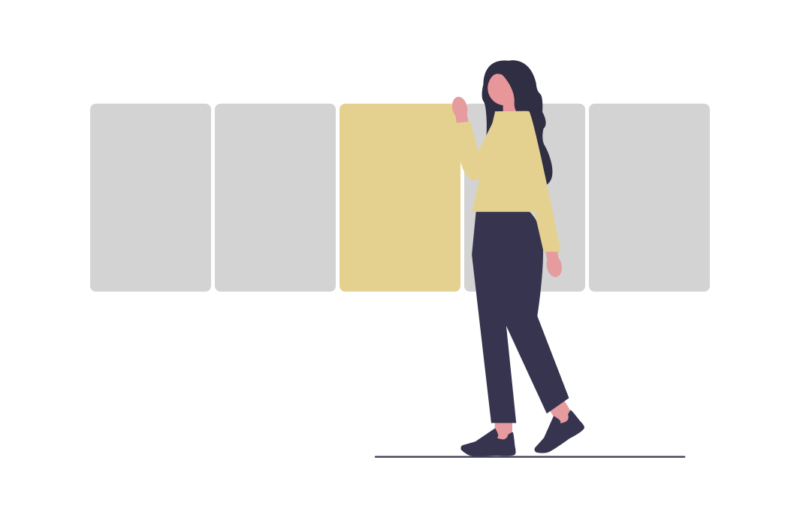
「みんな乗り越えているのだから」「今だけ我慢すれば」と自分を追い込む方もいるかもしれません。でもメンタルが弱っているときはこの方法は逆効果。
不本意な異動や年下の上司など組織の中でモヤモヤを抱えたときはまず自分の感情を認めてあげてください。「なぜもっと強くなれないのか」と自分を責める方が多くいます。メンタルが落ちているときは、そのままの自分を受け入れメンタルを落ち着かせることを優先。
こういった状況に直面すると誰しもストレスを感じるのは自然なこと。気分転換をしたりメンタルヘルスケアアプリを活用したりと自分に合ったストレス解消法を見つけることが大切です。最近ではAIを活用して心の健康状態をチェックできる「Awarefy」が話題のようです。
さいごに

元部下が上司になるというのは複雑でむずかしい状況ですよね。最初は戸惑いや不安ときには不満や葛藤を感じることも自然なこと。
このような状況を感情に振り回されるのではなく、むしろチーム全体の視点から見直してみると新たな可能性に満ちた転機として捉えることができます。
新しい上司との関係性を構築していく過程でコミュニケーションスキルや適応力が磨かれ、さらには自身の経験や知識を活かしながらチームに貢献する新しい方法を見出すことができるかもしれません。
変化に直面することは決してカンタンではありませんが、その中にある成長の機会を見出し積極的に活かしていくことで必ずや素晴らしい結果につながるはずです。