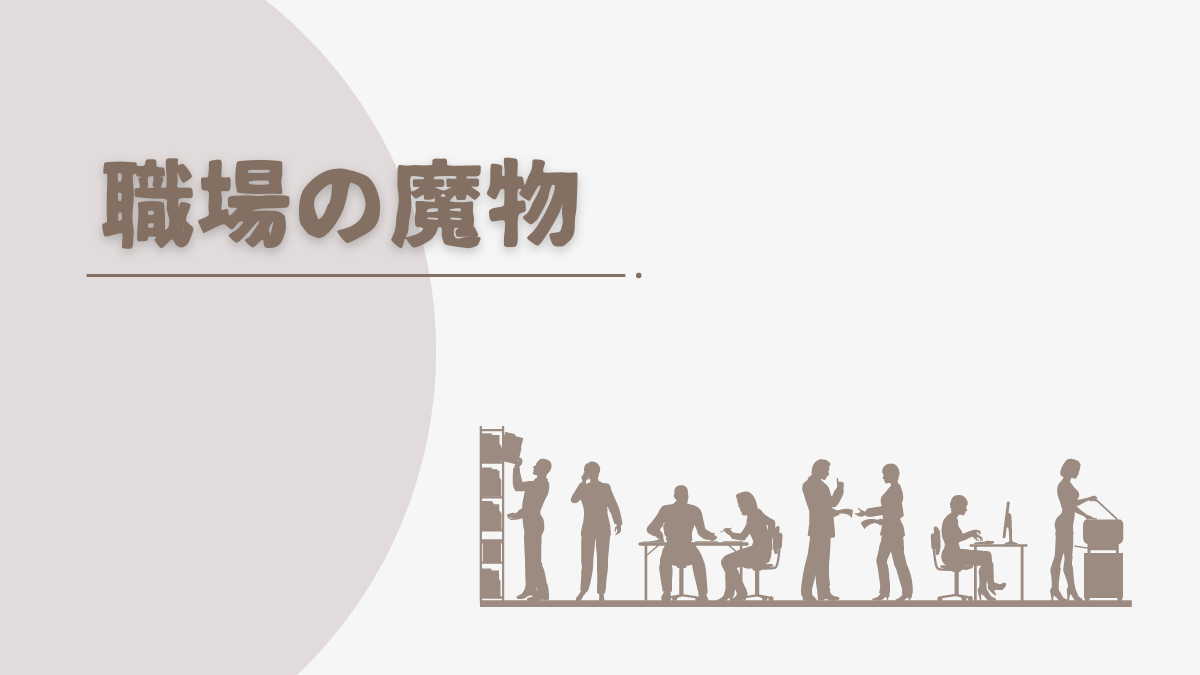職場でのハラスメントや不正って気になることがあってもなかなか言い出せないですよね。立場や周りの目が気になって声を上げるのはすごく勇気がいることだと思います。
でも最近「旧ジャニーズ」「兵庫県知事」「フジテレビ」の問題をきっかけに多くの会社がハラスメント対策に本気で取り組み始めていますね。この記事では職場でハラスメントを目にしたとき「できることは何か」について具体的な行動のヒントをお伝えしていきます。

「見て見ぬふり」しても自分を責めないで

職場のハラスメントを見かけても声を上げられなかった人は自分を責めすぎないでくださいね。「見て見ぬふりをした人も悪いでしょ」なんて言われることもありますが、これって私たちにとって大切な気づきになるんです。
というのも問題をずっと見過ごしてしまうとその状況はどんどん悪くなっていってしまうんですよね。周りの人たちも「まぁ、いいか」って感じで見過ごすようになって職場の雰囲気がどんどん重くなっていく…。
だからこそ「見て見ぬふりをした人も悪い」って言葉の本当の意味をみんなで考えてみる必要があるんです。
「見て見ぬふり」が生み出すこと

誰かが悪いことをしているのを見て「まぁいいか」って流してしまうと職場全体に大きく影響してしまう3つの怖いことがあるんです。
これらをちゃんと理解して対策を考えればもっと働きやすい職場になります。それでは具体的に説明していきますね。
被害者への二次被害
ハラスメントの被害者が我慢を続けると精神的・肉体的な健康に深刻な影響が出ます。長期間のストレスによって「うつ病」や「不眠症」といった心の健康問題が発生することも少なくありません。
さらに職場での不安や恐怖感から仕事への意欲を完全に失い退職を余儀なくされるケースも。被害者がもっとも深く傷つくのは「ハラスメントを受けているのに周囲から助けがないと感じる」強い孤立感と絶望感なんです。
加害者の増加
ハラスメントを見過ごしてしまうと加害者は「自分のやり方で大丈夫なんだ」と勘違いしてしまい、さらにひどい行為に走ってしまう可能性があるんです。
このように見て見ぬふりをすることで職場全体に「ハラスメントをしても大丈夫」という良くないメッセージが広がってしまいます。
とくに加害者が会社で重要な立場にいる場合は周りの人たちも「こういう行動も許されるんだ」と思い込んでしまい似たような問題行動が増えていってしまうかもしれません。
職場環境の悪化
職場でハラスメントが広がってしまうと社員同士の信頼関係がバラバラになってみんなが気まずい思いをしながら働くことになってしまいます。
そうなると「言いたいことも言えない雰囲気」になってしまってせっかくのアイデアも出せなくなり仕事の成果も上がらなくなってしまいます。
最悪の場合「もうここでは働けない…」と思って辞めてしまう人も出てくるかもしれません。
なぜ見て見ぬふりをするのか
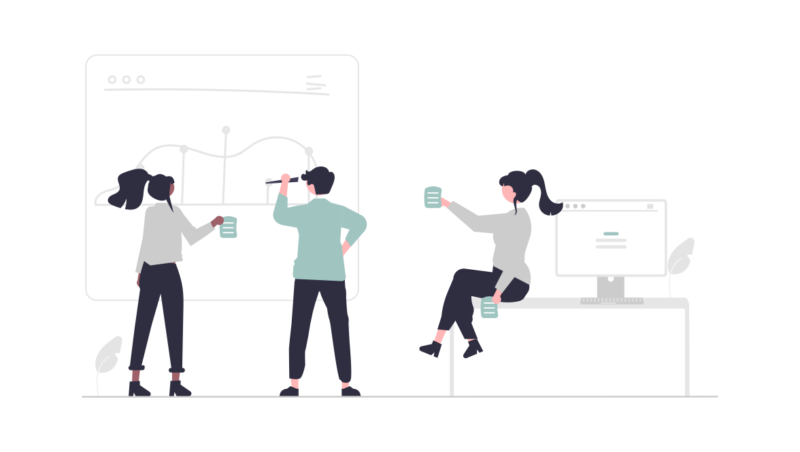
見て見ぬふりをする人の心理には主に3つの特徴があります。
- 責任の分散(誰かが行動してくれるだろう)「誰かが助けてくれるはず」と考えて自分から行動を起こさない状態。これは傍観者効果(ぼうかんしゃこうか)と呼ばれ周りに人が多いほど見て見ぬふりをする傾向が強くなります。つまり集団の中で他人の行動を見ているだけで自分は積極的に関わろうとしない心理状態。
- 危険回避(関わりたくない・自己保持)問題に関わることで自分自身が危険な立場に追い込まれることを恐れる心理。例えば、いじめの現場に介入することで自分が次のいじめの対象になるかもしれないと恐れるケース。
- 無関心(自分ごととして捉えられない)他者の問題に関心を持てず助けが必要な状況に気づかない、あるいは気づいても行動しようとしない心理。例えば他人の不幸や苦しみを自分のこととして実感できず心が動かされない状態。
得体の知れない空気・触れてはいけないものとは?
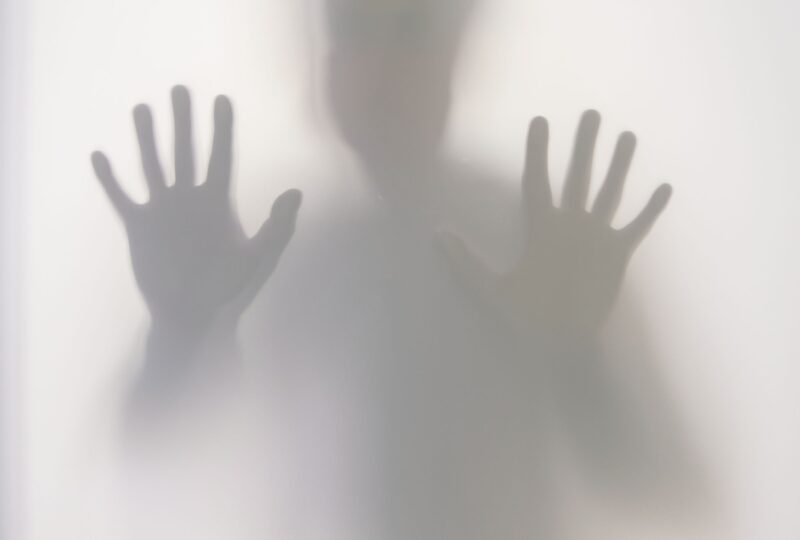
「なんだか得体の知れない…それには触れてはいけない空気があった」旧ジャニーズの記者会見でのこの言葉は多くの職場で起きている「見て見ぬふり」の文化を鋭く表現しています。
長年続いてきた不正や問題行為に誰も声を上げられない雰囲気。組織の闇に光を当てた旧ジャニーズの記者会見で語られた4つの重要なワード
- 見て見ぬふり
- 知っていた
- 触れてはいけない
- 得体の知れない空気
影響力のある人がまるで「絶対的な存在」になって誰も何も言えなくなる。その人の前ではビクビクしてしまうような。
一般企業でもこういうことって起きがちなんですよね。例えば部署のリーダーがそんな感じだったら「あの人、確かにパワハラっぽいけど仕事できるし出世もしてるから…まぁいいか」って思ってしまう。部下たちも「嫌われたくないし…」って我慢してそのうち職場全体が「これが普通」って思うように。
この旧ジャニーズの問題で私たちは見て見ぬふりをすることが、どれだけ怖い結果になるのかを考えさせられましたよね。
わたしたちが心がけること
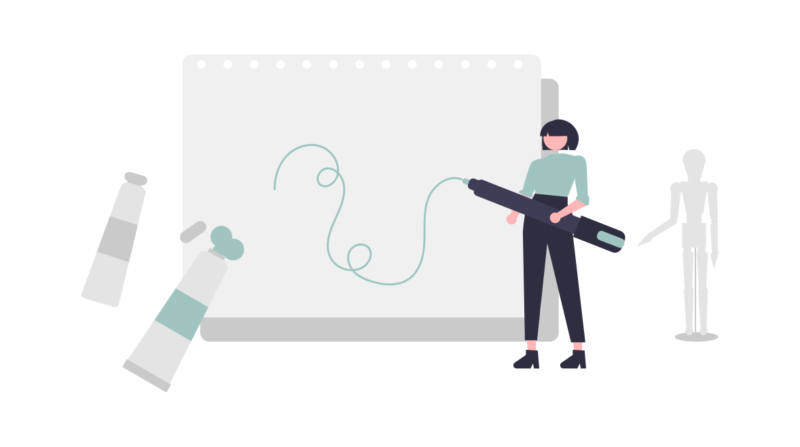
私たちが「見て見ぬふり」に対して、一人ひとりができる実践的な行動を3つ紹介します。すぐに始められて確実に効果が期待できる具体的なアクションです。
- ハラスメントについての正しい知識を身につける
- 日々の職場での会話や会議の内容に注意を払う
- 被害に遭われている方々をサポートする
ぜひ明日からでも取り入れてみてください。
ハラスメントについての正しい知識を身につける
ハラスメントにもいろんな種類があってそれぞれどんな形で起こるのかを知っておくことって働きやすい職場を作るためにとても大切なんです。
普段の何気ない言葉や態度の中にも「ハラスメント」の芽があることも。前もってどう対応すればいいのかを理解しておけば「これってどうしたらいいんだろう?」「どう動けばいいんだろう?」というときにもすぐに適切な判断ができるようになります。
当ブログ「職場のハラスメントについて」まとめ記事を用意しました。実際にあった事例をもとに「パワハラ」や「セクハラ」「無視」などの問題にどう対処したらいいのか関連する法律のことなども説明していますのでぜひチェックしてみてください。
日々の職場での会話や会議の内容に注意を払う
職場での会話や会議の中で「いつもと違う雰囲気やちょっと気になることはないかな?」って注意深く見てみましょう。
例えば「誰かの話が途中で遮られてないか」「特定の人ばかりが批判されてないか」「不公平な扱いを受けてないか」といった小さな変化に気づくことが大切。
ハラスメントを防ぐには目の前で起きていることに関心を持って「あれ?」と思ったら気にかけることが重要。ただ見ているだけじゃなくて職場の仲間としてみんなが気持ちよく働けるように気を配っていきたいですね。
被害に遭われている方々をサポートする
ハラスメントの被害に遭われている方を見かけたら少しだけ勇気を出して声をかけてみませんか。「大丈夫?」や「何かできることある?」といったひと言だけでも孤独と戦っているその方にとってはとても心強い支えになるはずです。
そういった声かけは被害に遭われている方に「あなたはひとりじゃない」というメッセージを伝える大切な機会に。
辛い経験をされている方は頭の中が混乱してどう行動すればよいか分からなくなっているかもしれません。気持ちが不安定になり自分の置かれている状況を客観的に見ることすらむずかしくなっている可能性も。
そんなときは一緒に記録を取ったり適切な相談窓口を探したり上司や人事への相談方法を考えたりとできる範囲でサポートしていきましょう。ひとりで声をかけづらい場合は信頼できる複数の仲間と協力しながら行動してみるのもよいでしょう。
小さな変化を起こす

ドラマみたいに「全部解決してやるぞ!」って勢いよくひとりで戦うのはちょっとむずかしいですよね。でもパワハラ上司がいる職場でも着実に良い方向に変えていけるとっておきの方法があるんです。
企業の人事として奮闘した日々や労働相談窓口で多くの方々の人間ドラマに立ち会った経験から実践的な解決策をお届けします!
経営陣や人事と気さくに話せる人を利用する
職場でハラスメントが起きていたら会社の担当部署に知らせる必要がありますよね。本来なら社内の相談窓口を使うのがベストなんですが実際にはあまり活用されていないのが現状。
だからまずは経営層や人事部門の中で話しやすそうな人を見つけましょう。現場で起きているハラスメントについて「どんな状況なのか」「被害を受けている人がどんな立場に置かれているのか」をできるだけ詳しく説明して問題がどれだけ深刻かを分かってもらうことが大切。
緊急性を伝えることでより素早い対応を期待。例えば「このまま何も対策を取らないと本人が行政機関に相談したりするかもしれません」というように伝えると会社側も対応の必要性を感じてくれるはずです。
ウワサ好きな人に実態を広めてもらう
職場には必ずと言っていいほどみんなの情報が集まる「ウワサ好き」や「情報通さん」がいますよね。そういう方々のコミュニケーション力を上手に利用させてもらいましょう。
こういう方々って大切な情報をさりげなく広められる素晴らしい才能の持ち主。ハラスメントの問題も自然な形で会社全体に広めてもらえるかもしれません。
共感する人を集める
じつはハラスメントの問題を解決するときに大切なのは同じ思いを持つ仲間を見つけることなんです。ハラスメントについて「おかしいな」って感じている人とおしゃべりする機会を作ってみましょう。
ランチタイムやちょっとした休憩時間に「最近こんなことがあってね…」って話してみるのもいいかも。そうやって少しずつ理解を深め合って誰もが安心して働ける職場を作る仲間の輪を広げていけたらいいですよね。
集団で行動する
ハラスメントの問題は個人で戦うのはとても大変。でも仲間と力を合わせればきっと良い方向に変えていけるはずです。みんなで行動することで「うちの会社ではハラスメントは絶対ダメ!」っていう強いメッセージを送ることができます。
一歩一歩は小さくても、いろんな方法を重ねていけばきっと職場は変わっていきます。
さいごに

職場の雰囲気を変えるのは本当に勇気のいることですよね。周りの人たちに「一緒に改善していきましょう」と声をかけるのも簡単ではありません。
でも小さな一歩が大きな変化のきっかけになるんです。「これっておかしいのでは?」と感じたら勇気を出して声を上げてみましょう。黙っているだけでは何も変わりませんから。
みんなで、おかしなことには「ちょっと待って!」と伝えていきましょう。そして何より大切なのはハラスメントで悩んでいる人に「一緒に頑張りましょう」と声をかけること。その温かい言葉がきっと大きな支えになるはずです。